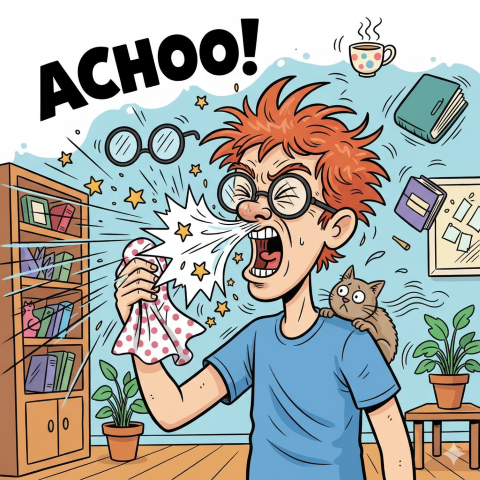面白いYouTubeがありました。
日本以外では、くしゃみをしたら返事をするそうです。面白いですね。
米国の大学で教えられていた先生に聞きましたら、「日本に来たネイティブは、近くの人がクシャミをしたら、さすがにBless you.とは声に出しませんが、口がBless you.と動いているのは分かる時があります。もう、反射的な癖な訳です。」と解説してくださいました。
動画翻訳
タイトル
Why Do We Say ‘God Bless You’ When Someone Sneezes?
なぜ私たちは誰かがくしゃみをしたときに「God Bless You(神の祝福がありますように)」と言うのか?
翻訳内容(要点の段階的展開)
「God bless you」という応答がどこから始まったのか正確に特定することはできませんが、これにはいくつかの有力な説があります。
1. 魂の流出を防ぐ説(古代の信仰)
- 大昔、人々はくしゃみをしたとき、鼻水(snot)だけでなく、魂(soul)も体から逃げ出してしまうと考えていました。
- もしこの説が真実であれば、「God bless you」と言うことは、その魂を守る助けをするためにできる最低限のことだと考えられていました。
2. 教皇による布告説(6世紀の疫病)
- もう一つの説は、6世紀のバチカン(Vatican)に関わるものです。この時代、ヨーロッパでは疫病(plague)が大流行し、多くの人々が命を落としました。
- 当時の教皇グレゴリウス1世(Pope Gregory I)は、誰かがくしゃみをするのを聞いたら、その人を守るために祝福を唱えるよう布告(decree)したと言われています。
- ペストの歴史 – Wikipedia
- グレゴリウス1世 (ローマ教皇) – Wikipedia
3. ペスト流行時の兆候説(14世紀)
- 時代は下って14世紀、ペスト(Bubonic Plague、別名:黒死病)が大流行した際にも、「God bless you」と言い始めた可能性があります。
- これは、くしゃみがペストに感染している兆候であるかもしれないと考えられていたためです。
4. 現代における意味合い
- 今日では、「God bless you」と言うことは、ほとんど意識せずに身についている反射的な反応(ingrained reaction)となっています。
- ある医師がニューヨーク・タイムズ紙に語ったところによると、この発言は「くしゃみに対する、ある種丁寧な応答」という以上の特定の意味を持たないものになっているとのことです。
5. その他の文化圏の代替表現
もし、くしゃみの後で、より高い力(higher power、神など)からの助けが必要ないと感じるなら、他の文化圏の代替表現を検討してみてください。
- ドイツ語では「Gesundheit(ゲズントハイト)」と言います。
- スペイン語圏の国々では「Salud(サルー)」と言います。
これらは大まかに「健康を祈る(a wishing of good health)」という意味に訳されます。
(情報提供:ケーシー・メンドーサ、Newsyシカゴ)
Scripps News | Latest News and In-Depth Coverage
世界の「くしゃみへの返事」一覧
| 国・地域 | 英語表現・現地語 | 日本語の意味 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 アメリカ | God bless you / Bless you | 神のご加護を | 最も一般的。宗教的というより習慣的。 |
| 🇬🇧 イギリス | Bless you | ご加護を | 日常的。短く言うのが普通。 |
| 🇨🇦 カナダ | Bless you | ご加護を | アメリカと同じく一般的。 |
| 🇦🇺 オーストラリア | Bless you | ご加護を | 丁寧な習慣として広く使われる。 |
| 🇮🇪 アイルランド | God bless you | 神のご加護を | カトリック文化の影響が強い。 |
| 🇩🇪 ドイツ | Gesundheit!(ゲズントハイト) | 健康を! | 直訳は「健康!」。英語圏でもよく使われる。 |
| 🇫🇷 フランス | À vos souhaits!(ア・ヴォ・スウェ) | あなたの願いがかないますように | ※2回目・3回目のくしゃみでは言葉が変わる場合も。 |
| 🇪🇸 スペイン | ¡Salud! | 健康を! | 乾杯のときの「サルー」と同じ言葉。 |
| 🇮🇹 イタリア | Salute! | 健康を! | スペイン語と同源。 |
| 🇷🇺 ロシア | Будь здоров! (Bud’ zdorov!)(ブーヂ ズダローフ!) | 健康でいてね! | 男性に対して。女性には「Будь здорова!」。(ブーヂ ズダローヴァ) |
| 🇨🇳 中国 | 长命百岁! (cháng mìng bǎi suì)(チャン ミン バイ スイ) | 長生きしますように | 古い言い方。今はあまり使わない。 |
| 🇯🇵 日本 | (特に言わない) | — | 「大丈夫?」や「風邪?」などと聞く程度。 |
| 🇰🇷 韓国 | 감기 걸렸어요? (風邪ひきましたか?)(カムギ コルリョッソヨ?) | 相手を気づかう言葉 | 礼儀として健康を心配するのが一般的。 |
※フランスでは、くしゃみの回数によって相手にかける言葉が変わる伝統的な慣習があります。
- 1回目: À tes souhaits! (ア・テ・スエ!) — 「あなたの願いが叶いますように」という意味です。
- 2回目: À tes amours! (ア・テ・ザムール!) — 「あなたの愛する人々に」という意味です。
- 3回目: Et qu’elles durent toujours! (エ・ケル・デュール・トゥジュール!) — 「そして、それら(願いと愛)が永遠に続きますように」という意味です。
- À tes souhaits ! ⇒ 対象 親しい間柄(家族、友人、恋人など)
- À vos souhaits ! ⇒ 目上・初対面の人、または複数人に対して
🇯🇵 日本でくしゃみに特別な返事がない理由
欧米などでくしゃみに対して「God bless you」と言う習慣があるのに対し、日本でそのような形式的な応答がないのは、くしゃみに対する根本的な捉え方や、文化・宗教的背景が異なるためです。
1. 文化的・俗信的な背景の違い
欧米の「God bless you」は、もともと「魂が体から抜けるのを防ぐ」「悪魔の侵入を防ぐ」「ペスト(疫病)から守る」といった、生命や健康を脅かす危険への対処として、神の力を借りるという切実な願いから生まれました。
1899年(明治32年)に海外から持ち込まれたペストが日本で初めて流行しました。日本でのペストの発生例は1926年(昭和元年)までで、その後は報告されていません。これは、当時の政府や北里柴三郎らの尽力による防疫対策(ネズミ駆除や検疫など)が功を奏したためです。
一方、日本のくしゃみに関する俗信(迷信)は、以下のようなもので、外部からの脅威というよりは、人間関係や運勢に結びつく傾向が強いです。
- 噂話の俗信:
- 日本では古くから「くしゃみをすると、どこかで誰かが自分の噂話をしている」という俗信があります。
- 回数によって意味が異なるとされることもあります(例:一回は褒められ、二回は悪口、三回は惚れられている、など)。
- この場合、くしゃみは生理現象というより人との繋がりを示すサインとして捉えられ、周囲の人がすぐに「神の加護」を祈る必要がありません。
- 万葉集の時代:
- 『万葉集』の歌には、くしゃみが「愛する人が自分のことを思っているから出る」という、比較的肯定的・ロマンチックな意味合いで使われていた例もあります。
2. 宗教的な背景の違い
- 欧米: キリスト教文化が根強く、くしゃみのような突発的な現象に対して「神の加護(God bless you)」を祈るという発想が自然に根付いています。
- 日本: 特定の一神教的な文化が公の生活の規範となっているわけではないため、日常生活の反射的な行為として「神の加護」を祈る習慣が生まれず、定着しませんでした。
3. 日本における一般的な対応
日本では、他人のくしゃみに対して形式的な返事をする習慣がない代わりに、もし咳やひどいくしゃみなどで相手が苦しそうにしていた場合は、以下のような一般的な気遣いの言葉をかけることがあります。
- 「大丈夫ですか?」
- 「お大事にどうぞ」
また、くしゃみをした本人も、周囲に対して迷惑をかけたことへの配慮として「失礼しました」と一言述べるのがマナーとされています。
くしゃみに関連する万葉集の歌と解説
1. うち鼻ひ 鼻をぞひつる 剣太刀 身に添ふ妹し 思ひけらしも
- 出典: 巻十一・2637 (寄物陳思・作者未詳)
- 読み下し文: うち鼻ひ 鼻をぞひつる 剣太刀(つるぎたち) 身に添ふ妹(いも)し 思ひけらしも
- 現代語訳: 大きなくしゃみが出た、またくしゃみが出た(何度もくしゃみが出る)。これは、腰にさした剣や太刀のようにいつも身に寄り添う妻が、今私のことを思っているからに違いない。
- 解説:
- この歌は、くしゃみが出ることを誰かに恋い慕われていることの前兆と捉える当時の俗信(恋の予兆)に基づいています。
- 「うち鼻ひ 鼻をぞひつる」は、「何度もくしゃみが出る」という様子を表しています。
- 「剣太刀 身に添ふ妹」は、常に身近にいる大切な妻を指す比喩表現です。
- 頻繁に出るくしゃみによって、作者は妻が自分のことを思ってくれているに違いないと確信する、愛情深い一首です。
2. 眉根掻き 鼻ひ紐解け 待つらむか いつかも見むと 思へる我を
- 出典: 巻十一・2408 (柿本朝臣人麻呂之歌集/正述心緒)
- 読み下し文: 眉根掻き 鼻ひ 紐解け 待つらむか いつかも見むと 思へる我を
- 現代語訳: (私を恋しく思うあまり)眉をかき、くしゃみをし、下紐を解いて、あの人は待っていてくれるだろうか。いつになったら会えるだろうかと思って来た私を。
- 解説:
- この歌には、恋の相手に逢える吉兆とされる三つの予兆が詠み込まれています。
- 眉根掻き(眉がかゆくなる)
- 鼻ひ(くしゃみが出る)
- 紐解け(下紐が自然に解ける)
- 「くしゃみが出る」ことは、恋人に逢える前兆の一つとして信じられており、作者は恋人が自分を恋しく思っている証としてこれらの予兆が彼女に現れているのか、と想像しています。
- この歌には、恋の相手に逢える吉兆とされる三つの予兆が詠み込まれています。
当時の「くしゃみ」に関する俗信
万葉集の時代、「くしゃみ」は現代のように病気や花粉症の症状としてではなく、誰かが自分を噂したり、恋い慕ったりしていることの合図(予兆)とされていました。
これは、現代でも残る「噂をされるとくしゃみが出る」という俗信のルーツとも言えるものです。特に万葉集では、「くしゃみ=恋の予兆」という文脈で使われることが多く、当時の人々の素朴で情熱的な恋心が垣間見えます。
この記事を書いた人
村坂 克之
小又接骨院・鍼灸院の院長です。鍼師、灸師、柔道整復師の国家資格にて治療を行っています。屋号の小又(こまた)は、先祖の小谷屋亦治郎(亦=又)に由来します。文字入力は親指シフト(orz配列)ユーザー。
詳しくは院長略歴をご覧下さい。